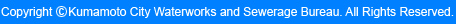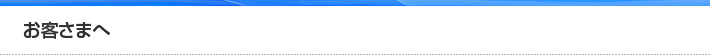
[最終更新日]2025年4月18日 11時22分
上下水道局では、災害などで断水した場合に備え、応急給水の備えをしています。
運搬給水とは、断水地域、各避難所、主要施設及び病院等重要施設に、給水車や給水タンク(車載型)で飲料水を運搬する給水方法です。即応力や機動力があるため、災害時の初動は、運搬給水が中心となります。
上下水道局では、災害のときに市民のみなさまに飲料水を届けるために、給水車を7台配備しています。ポンプを装備しているので、高いところにある受水槽に水を送ったり、低い場所の水をくみ上げたりすることが出来ます。また、被災地への災害時応援でも活躍しました。平成23年に発生した東日本大震災、平成24年に発生した九州北部豪雨災害、令和2年に発生した7月豪雨、令和6年に発生した能登半島地震などの災害発生時には、災害派遣を行っています。 
 災害時にトラック等に搭載し、運搬給水を行うためのタンクです。上下水道局では、1m3タンクを34個(うち折りたたみ式タンク17個)を備えています。
災害時にトラック等に搭載し、運搬給水を行うためのタンクです。上下水道局では、1m3タンクを34個(うち折りたたみ式タンク17個)を備えています。
消火栓は、道路上に100~200メートル間隔で設置されている消火用の水栓です。災害発生時には、消防等による消火活動だけでなく、応急給水にも活用します。
災害時等に、使用可能な消火栓がある場合は 路上の消火栓に専用の器具を接続し仮設給水所として活用します。
路上の消火栓に専用の器具を接続し仮設給水所として活用します。
 給水車等へ水を補給する際にも活用します。災害時ではありませんが、熊本城マラソンの開催時には、給水所へ水を補給するために消火栓を活用しています。
給水車等へ水を補給する際にも活用します。災害時ではありませんが、熊本城マラソンの開催時には、給水所へ水を補給するために消火栓を活用しています。
応急給水は、災害医療活動拠点病院や人工透析治療病院等の重要医療施設、重度身体障がい者施設や老人ホーム等の災害弱者施設、重要公共施設(市役所・区役所等)、避難所(小学校・公園等)で優先的に実施します。応急給水を実施する箇所・方法・時間は、災害の種類・規模・被害状況・断水範囲により異なります。応急給水活動を実施する際には、広報車両を用いて、現地広報(応急給水方法、実施場所、給水時間等の周知)を行います。
上下水道局では、給水基地(給水車等に水を補給するための基地)や災害対策用貯水施設(災害発生時に水を蓄えておく施設)の整備を進めています。災害時には、こうした施設で水を補給し、運搬給水を行います。

給水塔は、給水車に水を補給する施設です。上下水道局では、健軍水源地、上下水道局内、旧西部上下水道センター、川尻配水場、改寄配水場、城山送水場、富合東部水源地、八景水谷送水場の8施設に給水塔を設置しています。これらの施設は、災害時に応急給水を実施する際の給水基地となります。
 耐震化構造の貯水施設に緊急遮断弁を設置し、災害等の発生時に水を蓄えておくことが出来るようにした施設です。断水になった場合に備え、上下水道局では、災害時緊急貯水施設の整備を進めており、平成28年度末現在、健軍配水池を初め22ヶ所で60,050立方メートルの水を確保することが出来ます。詳しくは、配水池の耐震化と災害対策用貯水施設(リンク)をご覧ください。
耐震化構造の貯水施設に緊急遮断弁を設置し、災害等の発生時に水を蓄えておくことが出来るようにした施設です。断水になった場合に備え、上下水道局では、災害時緊急貯水施設の整備を進めており、平成28年度末現在、健軍配水池を初め22ヶ所で60,050立方メートルの水を確保することが出来ます。詳しくは、配水池の耐震化と災害対策用貯水施設(リンク)をご覧ください。